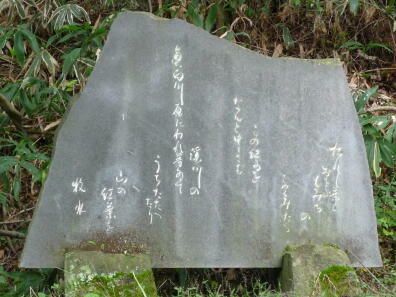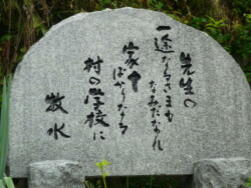–qگ…پ[”è‚جژچ‚جƒwƒbƒ_پ[
–qگ…پ[”è‚جژچ
ٹض“Œ‚Rپ@(ŒQ”nŒ§‡@پپپu‚ف‚ب‚©‚ف‹IچsپvٹضکA)
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<ŒQ”nŒ§‡A>‚ح‚±‚±‚ًƒNƒٹƒbƒNپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ ŒQ”n>‚ضپ@ŒQ”nŒ§‚ة‚ح‚Q‚Oˆبڈم‚ج–qگ…‰ج”è“™‚ھ‚ ‚é‚ھپA‚»‚ج‘ه”¼‚ح‘هگ³‚P‚P”N(1922)‚P‚OŒژپA’·–ىŒ§چ²‹v‚إ‚ج’Z‰ج‰ï‚ةچuژt‚ئ‚µ‚ؤڈµ‚©‚ꂽ–qگ…‚ھپA‚»‚جŒمپA‘گ’أپEژl–œپE–@ژtپEکVگ_‚ئ‚¢‚ء‚½‰·گٍ‚ة—§‚؟ٹٌ‚è‚ب‚ھ‚ç‹àگ¸“»‚ةژٹ‚éپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚ج—·پi‚P‚OŒژ‚P‚S“ْپ`‚Q‚W“ْپj‚ً‹L”O‚µ‚ؤŒڑ—§‚³‚ꂽ‚à‚ج‚إ‚ ‚éپB‚±‚جƒyپ[ƒW‚إ‚حپAپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚جچs’ِ‚ة‚µ‚½‚ھ‚ء‚ؤ‚»‚ê‚ç‚ج”è‚ً‚ـ‚ئ‚ك‚ؤ‚ف‚½پBپu‹IچsپvٹضکAˆبٹO‚ج‰ج”è‚حپA<ŒQ”nŒ§‡A>‚ةژûک^‚µ‚½پB
| پ@ŒQ”nŒ§پ@ڈ¬‰Jپ@کZچ‡(‚‚ة)ڈ¬ٹwچZپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬‘هژڑڈ¬‰J599-1 | ||
ڈ؛کa‚T‚O”N(197‚T)‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْڈœ–‹<70> |
||
پ@پu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚حپuڈ\Œژڈ\ژl“ْŒك‘OکZژڈہ’أ”پv‚إژn‚ـ‚éپB‚P‚T“ْچ²‹vژsٹâ‘؛“c‚إ‚ج’Z‰ج‰ï‚جŒمپA–ه’ي‚ç‚ئڈ¬ڈ”پEگ¯–ى‰·گٍپEŒyˆن‘ٍ‚ئ‰ٌ‚èپA‚»‚±‚©‚ç‚ح–ه—ر‚ئ‚¢‚¤گآ”N‚ئ“ٌگl’ع—ِپE‘گ’أ‰·گٍ‚ًŒo‚ؤپA‚P‚X“ْ‘ٍ“n‰·گٍ‚ً–عژw‚·پB پ[پ[پ@‚ئ‚è‚ا‚è‚ةچg—t‚µ‚½ژG–ط—ر‚جژR‚ًˆê—¢”¼‚ظ‚ا‚àچ~‚آ‚ؤ—ˆ‚é‚ئ‹}‚ة›س‚µ‚¢چâ‚ةڈo‰ï‚آ‚½پBŒ©‰؛‚·چâ‰؛‚ة‚ح‘ه‚«‚ب’J‚ھ—¬‚êپA‚»‚ج‘خٹف‚ة“¯‚¶—l‚ةگط‚è—§‚آ‚½ٹR‚ج’†‚ظ‚ا‚ة‚ح‰ئ‚جگ”ڈ\Œث‚©“ٌڈ\Œث‚©ˆêˆ¬‚è‚ة‚µ‚½‚ظ‚ا‚ج‘؛‚ھŒ©‚¦‚ؤ‚پB‹مڈ\‹مگـ‚ة‚ب‚آ‚½‚»‚ج‹}چâ‚ًڈ¬‘–‚è‚ة‘–‚èچ~‚é‚ئپAچâ‚جچھ‚ة‚à“¯‚¶—l‚ب‘؛‚ھ‚ ‚èپA•پ’ت‚ج•Sگ©‰ئˆل‚ح‚ب‚¢ڈ¬ٹwچZ‚ب‚ا‚àŒڑ‚آ‚ؤ‚پB‘خٹف‚ج‘؛‚حگ¶گ{‘؛پBٹwچZ‚ج‚ ‚é•û‚حڈ¬‰J‘؛‚ئ‰]‚س‚ج‚إ‚ ‚éپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹مڈ\‹مگـ‚¯‚ح‚µ‚«چâ‚ًچ~‚è—ˆ‚ê‚خ‹´‚ ‚è‚ؤ‚©‚©‚鋬‚جگ[‚ف‚ة پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚¨‚à‚ح‚ت‚ة‘؛‚ ‚è‚ؤ–¼‚ج‚₳‚µ‚©‚éڈ¬‰J‚ج—¢‚ئ‚¢‚س‚ة‚¼‚ ‚肯‚é پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ\ژ”‚¹‚µ‰ئ‚ة‚©‚ ‚ç‚ق‚ً•ا‚ً”²‚«‚ؤٹwچZ‚ئ‚ب‚µ‚آ•¨‹³‚ض‚ً‚è پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹwچZ‚ة‚à‚ج“ا‚ك‚éگ؛‚ج‚ب‚آ‚©‚µ‚³گg‚ة‚µ‚ف‚ئ‚ظ‚éژR—¢‰ك‚¬‚ؤپ@پ@پ@پ[پ[پ@پu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv پ@‰جڈW‚إ‚ح‘و‚P‚S‰جڈWپwژRچ÷‚ج‰جپx‚ج’†‚ةپu‚ ‚è‚ئ‚µ‚àژv‚ح‚ê‚تڈˆ‚ةŒـŒثڈ\Œث‚ظ‚ا‚ج‘؛‚ ‚è‚ؤ‚»‚ꂼ‚ê‚ةٹwچZ‚ًگف‚¯ژq‹ں‚½‚؟‚ة•¨‹³‚ض‚½‚èپBپv‚ئژŒڈ‘‚«‚µ‚ؤپAپuڈ¬‰J‘؛پv‚SژٌپAپu‘هٹâ‘؛پv‚QژٌپAپuˆّڈہ‘؛پv‚RژٌپAپuژl–œ“’Œ´‘؛پv‚PژٌپAپu‰iˆن‘؛پv‚Pژٌ‚ھژû‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپiپu‹Iچsپv‚ئ‚حˆê•”•\‹L‚ھˆظ‚ب‚éپjپB پ@‚©‚آ‚ؤ‚حڈ¬ٹwچZ‚جگ³–ه‘O‚¾‚ء‚½‚»‚¤‚إ‚ ‚é‚ھپAŒ»چف‚حٹwچZ‚جگخٹ_‚ً”w‚ةکZچ‡ژxڈٹ‚©‚çٹwچZ‚ض‚جگMچ†‚ً“n‚ء‚½‚·‚®–ع‚ج‘O‚ة‚ ‚é—RپB‰ج‚ًٹِں|‚µ‚½‚à‚ج‚ھ‚ب‚پAƒyƒ“ڈ‘‚«‚ج‰جچe‚ًٹg‘ه‚µ‚½•¶ژڑ‚ھچڈ‚ـ‚ê‚ؤ‚¢‚éپB |
||
| پ@پ@ <‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@کZچ‡ڈ¬ٹwچZ>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§’†”Vڈً’¬پ@گ¶گ{‰ج”艑‡U | |
•½گ¬‚V”N(1995)‚P‚PŒژ |
|
 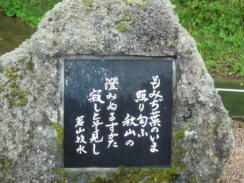 پ@ پ@
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@کI‘ڑ‚ج‰ً‚‚é‚ھ”@‚“V‚آ“ْ‚جŒُ‚ً‚س‚‚ف‚ة‚ظ‚س‚à‚ف‚ہ—tپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پwژRچ÷‚ج‰جپxپ@چg—t‚ج‰ج(‚P‚Oژٌ) پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚à‚ف‚ہ—t‚ج‚¢‚ـڈئ‚è‚ة‚ظ‚سڈHژR‚جگں‚ف‚ت‚éژp‚³‚ر‚µ‚ئ‚¼Œ©‚µ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰؛‘گ‚ج”–‚ظ‚ظ‚¯‚ؤŒُ‚肽‚éŒح–ط‚ھŒ´‚ج‘ي–ط’¹‚ج‚±‚ïپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ ‘ي–ط’¹‚ئ‘é(‚P‚Tژٌ) پ@‰ج”艑‚ح•½گ¬‚V”NپA’nŒ³‚جˆ¤چDژز‚ھ–qگ…‚ًژأ‚ٌ‚إ‘¢‚ç‚ꂽ‚à‚ج‚إپAپuژلژR–qگ…‚ج•à‚ٌ‚¾‚±‚ج“¹پ@‚»‚جگص‚ً•ç‚ء‚ؤ‘؛گl‚ھپA’Z‰ج‚ً‚آ‚‚ء‚½پBپv‚ئ‚ج—§‚ؤژD‚ئ‚ئ‚à‚ةپA“y’n‚جگl’B‚ج‘½‚‚ج‰ج”è‚ھ•ہ‚ٌ‚إ‚¢‚éپB |
|
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ گ¶گ{‰ج”艑>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§پ@•éچâ“»“¹پi“’‚ج•½‰·گٍ“üŒûپjپ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬ | ||
ڈ؛کa‚T‚Q”N(1977)‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْڈœ–‹<76> |
||
پ@‰جڈWپwژRچ÷‚ج‰جپx‚إ‚حپuچg—t‚ج‰جپv‚ةپuڈ\Œژڈ\ژl“ْ‚و‚èڈ\ˆêŒژŒـ“ْ‚ـ‚إگM”Zڈم–ى‰؛–ىڈ”چ‘‚جژR’J‚ً—ًڈ„‚éپBپwچg—t‚ج‰جپx‚و‚èپw–آ’ژژR‚جژپx‚ة“‚é‚ـ‚إ‚»‚ج—·‚ة‚ؤ‰r‚فڈo‚إ‚½‚é‚ب‚èپBپv‚ئ‚جژŒڈ‘‚ھ•t‚³‚ê‚ؤ‚¨‚èپA‚P‚PŒژ‚T“ْڈہ’أ‚جژ©‘î‚ة–ك‚é‚ـ‚إ‚جˆêکA‚ھ‚ـ‚ئ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپBˆê•ûپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚حپA—کچھگى‚جˆêگ…Œ¹‚ة‚½‚ا‚è‚آ‚¢‚½ٹ´“®‚ًŒّ‰ت“I‚ة•\Œ»‚·‚邽‚كŒQ”n‚©‚ç“ب–ط‚ض‚ئŒ§‹«‚ً‰z‚¦‚½‚ئ‚±‚ë‚إڈI‚ي‚ء‚ؤ‚¨‚èپA‚»‚êˆبچ~‚حپu‹àگ¸“»‚و‚è–ىڈBکH‚ضپv‚ئ‚µ‚ؤ‚ـ‚ئ‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@Œح‚ꂵ—t‚ئ‚¨‚à‚س‚à‚ف‚ہ‚ج‚س‚‚ف‚½‚邱‚جچg‚î‚ً‚ب‚ة‚ئگ\‚³‚قپ@پ@پ@پ@چg—t‚ج‰جپ@پi‚»‚جˆêپj پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ںâگى‚جگ^”’گىŒ´‚ة‚ي‚ê“™‚î‚ؤ‚¤‚؟‚½‚½‚ض‚½‚èژR‚جچg—t‚ً پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚µ‚ك‚肽‚é—ژ—t‚ً“¥‚ف‚ؤ‚ي‚ھ‹}‚®Œü‚ذ‚جژR‚ة”R‚ن‚é‚à‚ف‚ہ—tپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پi‚»‚ج“ٌپj |
||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ “’‚ج•½‰·گٍ“üŒû>‚ضپ@ |
| پ@ŒQ”nŒ§پ@‰ش•~‰·گٍ‡Tپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬ˆّڈہ(?) | ||||
Œڑ—§“ْ•s–¾ |
||||
پ@ پ@گ¶گ{‚ً‰ك‚¬پAپu‚¸‚آ‚ئˆê–{‚¾‚¯‘±‚¢‚ؤ—ˆ‚½–ى’†‚جپ@کH‚ھ•sˆس‚ة“ٌ‚آ‚ة•ھ‚ê‚éڈˆ‚ة—ˆ‚½پBڈ¬‚³‚ب“¹•W‚ھپ@—§‚ؤپT‚ ‚éپBH‚پA‰E‘ٍ“n‰·گٍ“¹پAچ¶‰ش•~‰·گٍپ@پ@“¹پBپv‚µ‚خ‚ç‚‚ح‘ٍ“n‚ض‚ج“¹‚ً‚½‚ا‚è‚ب‚ھ‚çپA‚Rپ`‚S”Nپ@‘Oپuچ‚‚¢ٹR‚جگ^‰؛‚جٹâ‚ج‚‚ع‚ف‚ة—N‚«پA‘گ’أ‚ئˆل‚آپ@‚ؤ“’‚ھگں‚ف“§‚آ‚ؤ‹ڈ‚éŒج‚ةپA‚»‚جٹR‚ةچç‚çUçP‚âپ@پ@‘´‘¼‚ج‰ش‚ھ‚ف‚ب“’‚جڈم‚ة‰e‚ً—ژ‚·پA‚ـ‚é‚إ’ê‚ة‰شپ@‚ً•~‚¢‚ؤ‚î‚é—l‚¾‚©‚ç‰ش•~‰·گٍ‚ئ‚¢‚سپv‚ئ•·‚¢‚½پA‚»پ@‚ج‰·گٍ“¹‚ض‚ئˆّ‚«•ش‚·پB پ@پu‘R‚µپA“r’†‚إ‚âپT‚±‚جژv‚ذ—§‚؟‚جŒم‰÷‚¹‚ç‚éپT‚ظپ@‚اکH‚ح‰“‚©‚آ‚½پB(—ھ)ˆّڈہ‘؛‚ئ‚¢‚س‚ج‚ة‚حڈ¬ٹwچZ‚ھپ@‚ ‚èپAژRˆü‚ج‚à‚¤“ْ‚à•é‚ꂽ’n–ت‚ً“¥‚ف–آ‚炵‚ب‚ھ‚çˆêگl‚ج”Nٹٌ‚آ‚½گوگ¶‚ھ“ٌڈ\گl‚ظ‚ا‚جگ¶“k‚ة‘ج‘€‚ً‹³‚ض‚ؤ‚پB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گوگ¶‚جˆê“r‚ب‚邳‚ـ‚à‚ب‚ف‚¾‚ب‚ê‰ئڈ\‚خ‚©‚è‚ب‚é‘؛‚جٹwچZ‚ة پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ذ‚½‚ذ‚½‚ئ“y“¥‚ف–آ‚炵گ^—‡‘«‚ةگوگ¶‚ح‹³‚س‚»‚ج‘ج‘€‚ً پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گوگ¶‚ج“ھ‚ج“أ‚à‚½‚س‚ئ‚¯‚êچںڈˆ‚ةژ€‚ب‚ق‚ئ‹³‚س‚é‚ب‚ç‚ك
پ@پ@ٹR‚ًچ~‚è‹´‚ً“n‚èˆêŒ¬‚ج“’ڈh‚ة“ü‚آ‚ؤگو‚أ“’‚ًپ@گu‚‚ئپA’낳‚«‚ً—¬‚ê‚ؤ‚î‚éŒk—¬‚جگى‰؛‚ج•û‚ًژw‚´پ@‚µ‚ب‚ھ‚çپAگىŒü‚¤‚جژR‚جˆü‚ةچف‚é‚ئ‚¢‚سپB(—ھ)‚ذ‚½‚ذپ@‚½‚ئگ£‚ة‚آ‚«‚³‚¤‚بٹë‚¢”آ‹´‚ً“n‚آ‚ؤ‚ف‚é‚ئپA‚ب‚é‚ظپ@‚ا‘´ڈˆ‚جگط‚è‚»‚¢‚¾—l‚بٹR‚جچھ‚ة“’‚ھ’X‚ض‚ؤ‚پBپ@‘ٹ•ہ‚ٌ‚إ“ٌ‰سڈٹ‚ة—N‚¢‚ؤ‚î‚éپBˆê‚آ‚حٹ•ک‚ج‰®چھپ@‚ھ‚ ‚èپAˆê•û‚ة‚ح‰½‚à–³‚¢پB(—ھ) پ@پ@ŒkŒü‚¤‚à‚»پT‚è—§‚آ‚½ٹâ‚جٹRپA‚¤‚µ‚ë‚ً‹آ‚°‚خچX‚ةپ@’_‚à—â‚ن‚ׂ«’fٹR‚ھ‚ج‚µ‚©پT‚آ‚ؤ‚î‚éپBٹR‚©‚çگ^‰،‚ة‚¢‚ë‚¢‚ëںَ–ط‚ھژ}‚ً’£‚آ‚ؤگ¶‚ذڈo‚إپA‘ه•ûژU‚è‚آ‚‚µ‚½چg—t‚ھ‚ب‚ظ‹ح‚©‚ة‚»‚جڈ¬ژ}‚ة–¼ژc‚ً‚ئپU‚ك‚ؤ‚î‚éپB‚»‚ê‚ھˆê‚ذ‚ç“ٌ‚ذ‚ç‚ئ’fٹش‚ب‚‰ن“™‚جڈم‚ةژU‚آ‚ؤ—ˆ‚éپBŒ©‚ê‚خ‘´ڈˆ‚ةˆê“ٌ‰H‚جٹ~’¹‚ھ—V‚ٌ‚إ‚î‚é‚ج‚إ‚ ‚آ‚½پB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گ^—‡‘ج‚ة‚ب‚é‚ئ‚ح‚µ‚آ‚آٹo‘©‚بچںڈˆ‚ج‰·گٍ‚ة‰®چھ‚ج–³‚¯‚ê‚خ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ٹ~’¹‚ھ“¥‚ف‚±‚ع‚·چg—t‚‚ê‚ب‚î‚ة“§‚«‚ؤ‚¼ژU‚è—ˆ‚ي‚ھŒ©‚ؤ‚ ‚ê‚خ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@“ٌ‰H‚ئ‚ج‚فژv‚ذ‚µ‚à‚ج‚ًژO‰Hژl‰Hٹ~’¹‚‚è‚»‚جچg—t‚ج–ط‚ة |
||||
| |
| پ@ŒQ”nŒ§پ@‰ش•~‰·گٍپ@ٹضگ°ٹظ–{ٹظپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬‘هژڑ“üژR1530 | ||
•½گ¬‚P‚Q”N(2000)‚PŒژڈœ–‹ |
||
پ@‚Q‚O“ْپu–¢–¾‚ة‹N‚«پA—m“•‚ج‰؛‚إ’©گH‚ً‚ئ‚èپA‚ـ‚¾‘«‚à‚ئ‚ج‚¤‚·ˆأ‚¢‚¤‚؟‚ة‘´ڈˆ‚ً—§‚؟ڈo‚إ‚½پB‹ء‚¢‚½‚ج‚حپA‚»‚ج‘«‚à‚ئ‚ة”ء‚ç‚ةگل‚ج—ژ‚؟‚ؤ‚î‚邱‚ئ‚إ‚ ‚آ‚½پB(—ھ)‰“‚‚ًŒ©‚é‚ئپA‘Q‚’©‚جŒُ‚ج‚³‚µ‚»‚ك‚½‚ً‚؟‚±‚؟‚ج•ô‚©‚ç•ô‚ھگ^”’‚ة‹P‚¢‚ؤ‚î‚éپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ذ‚ئ–éگQ‚ؤ‚ي‚ھ—§‚؟ڈo‚أ‚éژR‚©‚°‚ج‚¢‚إ“’‚ج‘؛‚ةگلچ~‚è‚ة‚¯‚è پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈم–ى‚ئ‰zŒم‚جچ‘‚ج‚³‚©‚ذ‚ب‚é•ô‚جچ‚‚«‚ةگلچ~‚è‚ة‚¯‚è پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ح‚¾‚ç‚©‚ةگل‚جŒ©‚ن‚é‚حw‚جگX‚جچ•–ط‚جژR‚ةچ~‚ê‚éŒج‚ة‚¼ پ@ٹضگ°ٹظ–{ٹظ‚ح–¾ژ،‚R‚S”N(1901)‚ة‘n‹ئ‚µ‚½‚ھپA•½گ¬‚Q‚O”N(2008)‚WŒژ‚R‚P“ْ‚ً‚à‚ء‚ؤ•آٹظپB‰ش•~‰·گٍ‚ج‰œگKڈؤ‰·گٍ‚ةڈ؛کaŒ³”N(1926)ٹJ‹ئ‚جٹضگ°ٹظ•تٹظ‚ھ‚Q‚Q”N(2010)ٹضگ°ٹظ‚ئ‚µ‚ؤ‰c‹ئ‚µ‚ؤ‚¢‚éپB |
||
| |
| پ@ŒQ”nŒ§’†”Vڈً’¬پ@–qڈê•t‹ك(–qگ…ƒRپ[ƒX“üŒû) ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬ | ||
ڈ؛کa‚T‚R”N(1978)‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْڈœ–‹<77> |
||
پ@‰ش•~‚ض‚ئƒRپ[ƒX‚ً•د‚¦‚½“¹’†پ[پuچ،‚ـ‚إ‚و‚è‚ح›س‚µ‚¢–ىکH‚ج“o‚è‚ئ‚ب‚آ‚ؤ‚پB—§Œح‚ج“è‚ھ‚آپU‚«پA‚ً‚è‚ً‚èŒI‚ج–ط‚àچ¬‚آ‚ؤں{‚ئ‹¤‚ةڈخ‚ف‚ي‚ꂽ‚»‚جژہ‚ًچھ‚ھ‚½‚ة—ژ‚µ‚ؤ‚پB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—[“ْ‚³‚·Œح–ى‚ھŒ´‚ج‚ذ‚ئ‚آکH‚ي‚ھ‹}‚®کH‚ةژU‚ê‚éŒI‚جژہ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰¹‚³‚â‚®—ژ—t‚ھ‰؛‚ةژU‚è‚ؤ‚ً‚邱‚جŒI‚جژہ‚جگF‚ج‚و‚낵‚³ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژؤŒI‚جژؤ‚جŒح—t‚ج‚ب‚©‚خ‚¾‚ة”@‚©‚ت‚؟‚ذ‚³‚«ŒI‚ج–،‚و‚³ |
||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@–qڈê•t‹ك>‚ضپ@ |
| پ@ŒQ”nŒ§پ@•éچâ“»ژچ”è پ@پ@پ@پ@پ@ ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬ | ||
ڈ؛کa‚R‚Q”N(1957)‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْڈœ–‹<21> |
||
پ@–qگ…—Bˆê‚جژچ”è‚إ‚ ‚èپA‚¨‚»‚ç‚چإ‚à‘ه‚«‚بƒ‚ƒjƒ…ƒپƒ“ƒgپBڈم‚ج–qگ…‘œ‚حڈ؛کa‚U‚Q”N(1987)‚ةچى‚è‘ض‚¦‚ç‚êپAŒ³‚ج‘œ‚ح’†”Vڈً’¬—ًژj–¯‘ژ‘—؟ٹظ‚ة“Wژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚¢‚¤پBژچ‚حگڈ•MڈWپwژ÷–ط‚ئ‚»‚ج—tپx‚ةژû‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB پ@–qگ…‚ج—·‚ھ‚à‚ئ‚ة‚ب‚ء‚ؤپAچ،‚±‚جƒ‹پ[ƒg‚حپu“ْ–{ƒچƒ}ƒ“ƒ`ƒbƒNٹX“¹پv‚ئŒؤ‚خ‚êپA–ˆ”N‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْ‚ة‚ح”è‚ج‘O‚إپu–qگ…‚ـ‚آ‚èپv‚ھچs‚ي‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‚µ‚©‚µ–qگ…ژ©گg‚حپAپuچً“ْ‚ج’ت‚è‚ةکH‚ً‹}‚¢‚إ‚â‚ھ‚ؤ‚ذ‚ë‚ر‚ë‚ئ‚µ‚½Œحنٹ‚جŒ´پA—§Œح‚ج“è‚ج‘إ‘±‚¢‚½•éچâ“»‚ج‘ه‚«‚ب‘ٍ‚ةڈo‚½پB“»‚ً‰z‚¦‚ؤ–ٌژO—¢پAگ³Œك‹ك‚‘ٍ“n‰·گٍ‚ة’…‚«پAگ³‰hٹظ‚ئ‚¢‚س‚جپTژOٹK‚ةڈم‚آ‚½پBپv(پw‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپx)‚ئپA‚ظ‚ئ‚ٌ‚ا‘f’ت‚èڈَ‘شپB‰ج‚àژc‚³‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پB•Wچ‚‚P‚O‚W‚W‚چپA‘O–锑‚ـ‚ء‚½‰ش•~‰·گٍ‚ً‘«‰؛‚جˆأ‚¢‚¤‚؟‚ةڈo”‚µ‚½ژ‚ح‚ح‚¾‚ç‚ةگل‚ھگد‚à‚ء‚ؤ‚¢‚½‚ئ‚¢‚¤‚©‚çپAگو‚ً‹}‚¢‚¾‚©پB پ@–qگ…‚حپu‰ح‚جگ…ڈم‚ئ‚¢‚س‚à‚ج‚ة•sژv‹c‚بˆ¤’…‚ًٹ´‚¸‚é•ب‚ًژ‚آ‚ؤ‚î‚éپBپvپiپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv)‚ئڈ‘‚«پA‘هگ³‚V”N(1918)‚P‚PŒژ‚ة‚حپu‚ذ‚ئ‚آ—کچھگى‚ج‚ف‚ب‚©‚ف‚ًگq‚ث‚ؤŒ©‚و‚¤‚ئپvگ…ڈم‰·گٍ‚©‚ç“’•O‘]‚ـ‚إ‘k‚èپA‚³‚ç‚ة‚حٹض“Œ‚ج–ë”nںâ‚ئŒ¾‚ي‚ê‚éŒلچبŒk’J‚ب‚ا‚ً‰ٌ‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚±‚جپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚ج—·‚àپAپu•ذ•iگى‚ج‰œ‚ة•ھ‚¯“ü‚炤‚ئ‰]‚س‚ج‚حژہ‚حچ،“x‚ج—·‚جٹل–ع‚إ‚ ‚آ‚½پv‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپB‚V”N‚ج—·‚ج‰ج‚ح‘و‚P‚R‰جڈWپw‚‚ë“yپx‚ةپu‚ف‚ب‚©‚ف‚ضپv‚ئ‘肵‚ؤ‚P‚T‚Xژٌژû‚ك‚ç‚êپA‚ـ‚³‚ةپu‚ف‚ب‚©‚فپv‚ض‚ج“²‚ê‚ھ‹‚•\‚ê‚ؤ‚¢‚éپBپ@ |
||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ •éچâ“»>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§’†”Vڈً’¬‘هٹâپ@–qگ…‰ïٹظپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬‘هژڑڈم‘ٍ“n3405 | |||
پ@پ@پ@ڈ؛کa‚T‚O”N(197‚T)‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْڈœ–‹<71> |
|||
پ@–¾ژ،‚P‚Q”N(1879)‘؛’†‚جگlپX‚ھ‹¦—ح‚µ‚ؤŒڑ‚ؤپAڈ؛کa‚Q‚X”N(1954)گVچZژة‚ھ‚إ‚«‚é‚ـ‚إ’nˆو‚جٹwچZ‚ئ‚µ‚ؤژg‚ي‚ê‚ؤ‚«‚½‹Œ‘هٹâٹwچZپiŒڑ’z“–ڈ‰‚جژp‚إŒ»‘¶‚·‚é‹Mڈd‚بŒڑ•¨‚ئ‚µ‚ؤ’†”Vڈً’¬‚جڈd—v•¶‰»چà‚ةژw’èپjپBگVچZژة‚ضˆع“]‚جچغ‚ةپu•غ‘¶‚ً–ع“I‚ئ‚µ‚ؤپA–qگ…‚ج’تچs‚ة‚ ‚â‚©‚èپw–qگ…‰ïٹظپx‚ئ–½–¼‚³‚êپAˆبŒم‘هٹâ‚جگlپX‚جڈW‰ïڈٹ‚ئ‚µ‚ؤŒ»چف‚ةژٹ‚ء‚ؤ‚¢‚éپv‚ئگà–¾”آ‚ة‚ ‚éپB پ@پu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚ة‚ح‘هٹâ’n‹و‚ج‹Lڈq‚ھ‚ب‚پAڈ¬‰J‘وˆêڈ¬ٹwچZ‰ج”è‚ج—“‚ة‹L‚µ‚½‚و‚¤‚ةپAپwژRچ÷‚ج‰جپx‚ة‚Qژٌژû‚ك‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@گl‰ك‚®‚ئگ¶“k“™‚ح‚ف‚ب‘–‚¹ٹٌ‚è‚ؤٹ_‚و‚肼Œ©‚éٹwچZ‚ج’ë‚ج پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ي‚ê‚à‚ـ‚½‚©‚©‚è‚«‘؛‚جٹwچZ‚ة‚±‚جژq“™‚ج‚²‚ئ’ت‚éگlŒ©‚« |
|||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ –qگ…‰ïٹظ>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§’†”Vڈً’¬ژl–œ ŒلچبŒS’†”Vڈً’¬ژl–œ“’Œ´ | |||
ڈ؛کa‚T‚P”N(1976)‚P‚OŒژ‚Q‚P“ْڈœ–‹<72> |
|||
پ@‘ٍ“n‰·گٍ‚ةگ³Œك‹ك‚’…‚¢‚½–qگ…‚½‚؟‚حپA‰·گٍ‚ً—پ‚ر’‹گH‚ً‚ئ‚ء‚½ŒمپAژl–œ‰·گٍ‚ض‚ئڈo”‚·‚éپB‚µ‚©‚µپuچںڈˆ‚إڈ‡ڈک‚ئ‚µ‚ؤژl–œ‰·گٍ‚جژ–‚ًڈ‘‚©‚ث‚خ‚ب‚ç‚تژ–‚ً•s‰ُ‚ة‚¨‚à‚سپB‚¢‚©‚ة‚à•s‰ُ‚بˆَڈغ‚ً‘´ڈˆ‚ج‰·گٍڈh‚©‚çژَ‚¯‚½‚©‚ç‚إ‚ ‚éپBپv‚ئ‹L‚·پBپuˆê”‘ژز‚ج‚¹‚î‚ج‚ف‚إ‚ح‚ب‚©‚آ‚½‚ج‚¾‚وپB‰ù’†‚ً“¥‚ـ‚ꂽپvŒج‚ج‘e––‚بˆµ‚¢‚إ‚ ‚ء‚½پBپu‹كچ ‚و‚ژl–œپXپX‚ئ‚¢‚س—l‚ة‚ب‚آ‚½‚à‚ج‚¾‚©‚çژl–œگوگ¶‚·‚آ‚©‚è‘گ’أˆةچپ•غ‚ئŒ¨‚ً•ہ‚ד¾‚½‚آ‚à‚è‚ة‚ب‚آ‚ؤ•@‘§‚ھچr‚¢ŒXŒü‚ھ‚ ‚é‚ج‚¾‚炤‚ئژv‚سپAˆà‚حپUˆêژي‚جگ¬‹à‹C•ھ‚¾ƒlپBپv‚ئ‚ـ‚إŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپB پ@‚±‚ج‰ج‚حپA‚»‚جژl–œ‰·گٍ‚ة’…‚‘O‚ج‚±‚ئ‚إپA‚±‚ê‚àپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚ة‚حڈq‚ׂç‚ê‚ؤ‚¢‚ب‚¢پBپwژRچ÷‚ج‰جپx‚ةپuژl–œ“’Œ´‘؛پv‚ئ‚µ‚ؤ‚PژٌپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈ¬ٹwچZ‚¯‚س“ْ—j‚ة‚ ‚è‚ة‚¯‚èچ÷‚ج‚à‚ف‚ہ‚½‚¾‚ةژU‚è‚î‚ؤ پ@‚µ‚©‚µپA‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْ‚ح‹à—j“ْ‚إپA‰ج‚ج“à—e‚ئچ‡’v‚µ‚ب‚¢پB‘هŒه–@ژپ‚ة‚و‚é‚ئپAپwژRچ÷‚ج‰جپx•زڈW‚ةچغ‚µ‚ؤپAŒمڈq‚ج‰iˆن‘؛‚إ‚جچى‚ئ“ü‚ê‚؟‚ھ‚¦‚½‚à‚ج‚إ‚ ‚낤‚ئ‚¢‚¤پB |
|||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ ژl–œ“’Œ´>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§پ@ژOچ‘کH—^ژس–ىڈ»ژq‹Iچs•¶ٹwٹظ‘Oپ@ پ@پ@—کچھŒS‚ف‚ب‚©‚ف’¬‰ژƒ–‹‰·گٍ1175 | ||
•½گ¬Œ³”N(1989)‚P‚OŒژ‚Q‚Q“ْ(?) |
||
‘P‰q‚ئ‚¢‚¤‘nچىژذژذ—F‚ئپA—‚“ْ–@ژt‰·گٍ‚ةŒü‚©‚¤پB“r’†پuپw‰ژƒ–‹‘؛پx‚ئ‚¢‚س•sژv‹c‚ب–¼‚ج•”—ژپv‚ة‚â‚ح‚èژذ—F‚جڈ¼ˆن‘¾ژOکY‚ً–K‚ثپA”ق‚à—U‚ء‚ؤˆêڈڈ‚ة–@ژt‰·گٍ‚ضŒü‚©‚ء‚ؤ‚¢‚éپB پ@‰ژƒ–‹‚حŒأ‚چù‚ج“’‚ئ“’“‡‰·گٍ‚ئ‚¢‚¤‚Q‚آ‚ج‰·گٍڈê‚إ‚ ‚ء‚½‚ھپAڈ؛کa‚R‚R”N(1958)ƒ_ƒ€چHژ–‚إŒ»چف’n‚ةˆع“]‚µ‰ژƒ–‹‰·گٍ‚ئڈج‚·‚é‚و‚¤‚ة‚ب‚ء‚½‚ئ‚©پB–qگ…‚ح–@ژt‰·گٍ‚©‚ç‚ج‹A‚èپAپu‰ژƒ–‹‘؛‚ًڈoٹO‚ꂽ“¹‰؛‚جچù‚ج“’‰·گٍ‚إ’‹گH‚ً‚ئ‚آ‚½پB‘ٹ”—‚آ‚½’fٹR‚ج•ذ‘¤‚ج’†• ‚ةچف‚éˆêŒ¬‰ئ‚إپA‚»‚ج“ٌٹK‚©‚çژخ‚كگ^ڈم‚ة‘ٹگ¶‹´‚ھ‹آ‚ھ‚ꂽپBپvچù‚ج“’‰·گٍ‚جˆêŒ¬ڈh‚ح‘ٹگ¶ٹظپB پ@•¶ٹw”è‚حپA‰ژƒ–‹ƒzƒeƒ‹‚جڈ—ڈ«‚ھٹظ’·‚إ‚ ‚éپuژOچ‘کH—^ژس–ىڈ»ژq‹Iچs•¶ٹwٹظپ@’ضژR–[پvپi•½گ¬‚P‚R”NپuژOچ‘کH‹Iچs•¶ٹwٹظپv‚©‚çڈ»ژqگê–ه•¶ٹwٹظ‚ئ‚µ‚ؤ‰üڈجپj‘O‚ةپAŒü‚©‚ء‚ؤچ¶پuژلژR–qگ…•¶ٹw”èپv‰E‘¤‚ةپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚جˆêگك‚ًچڈ‚ٌ‚¾گخ”è‚ئ‚¢‚¤Œ`‚إŒڑ‚ؤ‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB‹ك‚‚ة‚حپu‰ج”è‚ج“¹پv‚ھ‚ ‚èپA‚»‚±‚ة‚àپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚جˆêگك‚ًچڈ‚ٌ‚¾‹Iچs•¶”è‚ھ‚ ‚é‚ئ‚¢‚¤پBپ@ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ |
||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ ژOچ‘کH‹Iچs•¶ٹwٹظ>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§پ@‰iˆنڈh‹½“yژ‘—؟ٹظپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—کچھŒS‚ف‚ب‚©‚ف’¬‰iˆن452-1 | |||
ڈ؛کa‚T‚S”N(1979)‚RŒژ‚Q‚X“ْڈœ–‹<82> |
|||
پ@‰iˆن‚ةٹض‚µ‚ؤ‚حپwژRچ÷‚ج‰جپx‚ج‚Pژٌ‚¾‚¯‚إپA‘¼‚ج‹Lڈq‚ح‚ب‚¢پB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژR‚©‚°‚ح“ْ•é‚ح‚â‚«‚ةٹwچZ‚ج‚ـ‚¾ڈI‚ç‚ت‚©–{“ا‚قگ؛‚· پ@‰ژƒ–‹‚جڈ¼ˆن‚ج‰ئ‚ًڈo‚½‚ج‚حپuŒكŒمژOژ‚ً‚·‚¬‚ؤ‚پB–@ژt‚ـ‚إ‚ح‚ب‚ظژO—¢پA‚و‚ظ‚ا‚±‚ê‚©‚ç‹}‚ھ‚ث‚خ‚ب‚ç‚تپBپvپuڈ¬‘–‚è‚ة‘–‚آ‚ؤ‹}‚¢‚¾‚ج‚إ‚ ‚آ‚½‚ھپAڈI‚ة‘S‚•é‚ê‚ؤ‚µ‚ـ‚آپv‚ؤ‚©‚ç–@ژt‰·گٍ‚ة“’…پB—‚’©پu‚¤‚·ˆإ‚جژc‚آ‚ؤ‚î‚éŒك‘OŒـژپAچً–é‚ج‘گèـ‚ج‚ـ‚¾ژ¼‚آ‚ؤ‚î‚é‚ج‚ًگْ‚«‚µ‚ك‚ؤ‚»‚جŒkٹش‚ج“’‚جڈh‚ً—§‚؟ڈo‚إپv“¯‚¶“¹‚ً–ك‚éپB‚µ‚©‚à‚Q‚Q“ْ‚ح“ْ—j“ْ‚إ‚ ‚ء‚½پB‚ئ‚¢‚¤‚±‚ئ‚إپA‘هŒه–@ژپ‚ح‚±‚ج‰ج‚حژl–œ“’Œ´‚إ‚جچى‚ئŒ¾‚ء‚ؤ‚¢‚éپBپ@پ@ |
|||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@‰iˆنڈh‹½“yژ‘—؟ٹظ>‚ضپ@ |
| پ@ŒQ”nŒ§پ@کVگ_‰·گٍپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈہ“cژs—کچھ’¬کVگ_پ@–qگ…‹´گ¼‘¤ | ||
ڈ؛کa‚U‚P”N(1986)‚RŒژڈœ–‹(?) |
||
پ@‚Q‚R“ْ“’ڈh‰·گٍپA‚Q‚S“ْڈہ“c‚إ‚»‚ꂼ‚ê‚P”‘‚µ‚½ŒمپAکVگ_‰·گٍ‚ضŒü‚©‚¤پBگ¶•û‹gژں‚ئ‚¢‚¤گآ”N‚ھ“¯چs‚µ‚½پB‚»‚µ‚ؤ‚Q‚U“ْپu‹N‚«‚ؤŒ©‚é‚ئپA‚ذ‚ا‚¢“ْکa‚ة‚ب‚آ‚ؤ‚پB(—ھ)ژ~‚ق‚ب‚‘طچف‚ئ‚«‚ك‚ؤ‘Q‚‚¢پT‹Cژ‚ةگŒ‚ذ‚©‚¯‚ؤ—ˆ‚é‚ئپA‹}‚ة‰JŒث‚جŒ„‚ھ–¾‚é‚‚ب‚آ‚½پBپwƒIƒ„ƒIƒ„پAگ°‚ê‚ـ‚·‚وپBپx‚³‚¤Œ¾‚س‚ئKپ[ŒN‚ح”ٍ‚رڈo‚µ‚ؤ”شژP‚ً”ƒ‚آ‚ؤ—ˆ‚½پBپv پ@‚»‚ج”شژP‚ة‘¦‹»“I‚ةڈ‘‚«•t‚¯‚ç‚ꂽ‚ج‚ھژں‚ج‚QژٌپBپuKپ[ŒNپv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھگ¶•û‹gژںپB پ@پ@پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‹gژںŒN‚ةٹٌ‚· پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚©‚ف‚آ‚¯‚ج/‚ئ‚ث‚جŒS‚ج/کVگ_‚ج/ژ‰J‚س‚é/’©‚ً•ت‚ê/‚ن‚‚ب‚è پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘هگ³ڈ\ˆê”Nڈ\Œژ“ùکZ“ْ/—·گl–qگ… پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ گŒ–q پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‚ب‚ظڈ‘‚«‚آ‚°‚éˆêژٌ پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‘ٹ•ت‚ê/‚ي‚ê‚ح“Œ‚ة/ŒN‚حگ¼‚ة/‚ي‚©‚ê‚ؤ‚ج‚؟‚à/ˆù‚ـ‚ق‚ئ‚¼/‚¨‚à‚س پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[پ[ پ@پ@پ@ |
||
پ@‚±‚ج”شژP‚جƒŒƒvƒٹƒJ‚حڈہ’أ‚ج–qگ…‹L”Oٹظ‚ة“Wژ¦‚³‚ê‚ؤ‚¢‚éپBڈہ“c‚جک®—رژ›‚ة‚à”شژP‚ً‚©‚½‚ا‚ء‚½‰ج”è‚ھپA–qگ…گ¶’a•S”N‹L”O‚ئ‚µ‚ؤڈ؛کa‚U‚P”N(1986)‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْŒڑ—§‚³‚ꂽ‚ئ‚¢‚¤پB پ@Œ»چفپu–qگ…‚ن‚©‚è‚جڈhپv‚ً‚¤‚½‚¤پu”’•ا‚جڈhپ@–qگ…‰‘پv‚حپAپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚ةپuڈh‚ة“ü‚آ‚ؤ“’‚ًگu‚‚ئپAڈ‚µ—£‚ê‚ؤ‚î‚ؤ‚¨‹C‚ج“إ‚إ‚·‚ھپA‚ئŒ¾‚ذ‚ب‚ھ‚çپA”w‚جچ‚‚¢کV–ê‚ھ’ٌ“”ژ‚آ‚ؤگو‚ة—§‚آ‚½پB‚ا‚جڈh‚ة‚à“à“’‚ح–³‚¢‚ئ•·‚¢‚ؤ‚‚ج‚إپA‰½‚ج‹C‚à‚ب‚‚»‚جŒم‚ةڈ]‚آ‚ؤŒثٹO‚ضڈo‚½‚ھپA‚±‚ê‚ح‚ـ‚½‰ش•~‰·گٍ‚ئ‚àˆظ‚آ‚½‚½‚¢‚ض‚ٌ‚بڈˆ‚ض“’‚ھ—N‚¢‚ؤ‚î‚é‚ج‚إ‚ ‚آ‚½پBژè•ْ‚µ‚إ‚حچ~‚è‚邱‚ئ‚àڈo—ˆ‚ت›س‚µ‚¢ٹR‚جٹâچâکH‚ًپAٹô“x‚©گـ‚ê‹ب‚آ‚ؤگh‚¤‚¶‚ؤگىŒ´‚ضڈo‚½پB‚»‚µ‚ؤ‚ـ‚½گخ‚جچr‚¢گىŒ´‚ً’H‚éپB‚»‚ج’†ڈB‚ج—l‚ة‚ب‚آ‚½گىŒ´‚ج’†‚ة’ل‚¢”آ‰®چھ‚ًگف‚¯‚ؤپA‚»‚ج‰؛‚ة—N‚¢‚ؤ‚î‚é‚ج‚¾پBپv‚ئ‚ ‚éپu”w‚جچ‚‚¢کV–êپv‚ج‚ذ‘·‚ھڈ—ڈ«‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚é‚ئ‚©پBپ@ |
||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ کVگ_‰·گٍ>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§ڈہ“cژsپ@ŒIگ¶ƒgƒ“ƒlƒ‹“üŒûپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ڈہ“cژs”’‘ٍ’¬چ‚•½ | ||
ڈ؛کa‚U‚P”N(1986)‚P‚OŒژ‚Q‚O“ْڈœ–‹ |
||
پ@ڈہ“c‚©‚çکVگ_‰·گٍ‚ضپuکH‚ح‚¸‚آ‚ئ•ذ•iگى‚جٹف‚ة‰ˆ‚¤‚½پB‚±‚ê‚حژہ‚ح‹Œ“¹‚إ‚ ‚é‚ج‚¾‚³‚¤‚¾‚ھپAŒج‚ç‚ةژ„‚ح‚±‚ê‚ًگï‚ٌ‚¾‚ج‚إ‚ ‚آ‚½پBپv‚ئ‚¢‚¤“¹‚ً‚½‚ا‚ء‚ؤ‚¢‚éپBˆê•ûŒIگ¶ƒgƒ“ƒlƒ‹‚ح—ر“¹گش‘qŒIگ¶گü‚ة‚ ‚èپA–qگ…‚ھ’ت‚ء‚½“¹‚ئ‚ح‚¨‚»‚炈ل‚ء‚ؤ‚¢‚é‚à‚ج‚ئژv‚ي‚ê‚éپB‚ب‚؛‚±‚±‚ة‰ج”è‚ھ‚ ‚é‚ج‚©‚ح•s–¾پBƒlƒbƒg‚إپuŒIگ¶ƒgƒ“ƒlƒ‹پv‚ًŒںچُ‚·‚é‚ئپAپuŒQ”nŒ§‚إ—Lگ”‚جگS—ىƒXƒ|ƒbƒgپv‚ئ‚ ‚é‚ھپBپ@ |
||
| پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ ŒIگ¶ƒgƒ“ƒlƒ‹>‚ض |
| پ@ŒQ”nŒ§•ذ•i‘؛پ@”’چھ‹›‰‘پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@—کچھŒS•ذ•i‘؛“Œڈ¬گى4653 | ||
ڈ؛کa‚S‚T”N(1970)‚UŒژڈœ–‹<57> |
||
پ@‚Q‚U“ْگ¶•û‚ئ•ت‚ꂽ–qگ…‚حپAٹغڈہ‚ج–گ—{گB‚ج”شڈ¬‰®‚ة”‘‚ك‚ؤ‚à‚炤‚½‚ك“Œڈ¬گى‘؛‚جگç–¾‰ئ‚ً–K‚êپA‚»‚ج“ْ‚ح”’چھ‰·گٍ‚ة”‘‚ـ‚éپB‚»‚µ‚ؤ—‚“ْپAٹغڈہ‚ض‚ئŒü‚©‚¤‚ج‚إ‚ ‚é‚ھپA‰ج‚ح‚»‚ج“r’†‚إ‚ج‚à‚جپB”’چھ‹›‰‘‚حگç–¾‰ئ‚ھŒo‰c‚µپAƒjƒWƒ}ƒX‚ب‚ا‚P‚O‚O–œ”ِ‚ج‹›‚ً—{گB“™‚µ‚ؤ‚¢‚éپu‰œ“ْŒُ‚جƒtƒ@ƒ~ƒٹپ[ƒ‰ƒ“ƒhپv‚ئ‚¢‚¤‚ج‚ھŒ»چف‚ةوگ‚¢•¶‹ه‚إ‚ ‚é‚و‚¤‚¾‚ھپA‚»‚±‚جژ÷—î‚W‚O‚O”N‚ً‚±‚¦‚éƒ^ƒ`ƒ„ƒiƒM‚ج‰؛‚ة‰ج”è‚ھ‚ ‚éپB•¶ژڑ‚ح–qگ…‚جژيپX‚ج•Mگض‚©‚çڈW‚ك‚½‚ئ‚¢‚¤پB پ@پwژRچ÷‚ج‰جپx‚ة‚حپAپuڈم–ى‚جچ‘‚و‚è‰؛–ى‚جچ‘‚ض‰z‚¦‚ق‚ئ‚ؤ•ذ•iگى‚جگ…Œ¹—ر‚ً‰ك‚®پBپv‚ئ‚µ‚ؤ‚P‚OژٌپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@‰؛‘گ‚جچù‚ج‚µ‚°‚ف‚جŒُ‚è‚î‚ؤ‚ب‚ç‚رٹ¦‚¯‚«“~–ط—§‚©‚à پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@ژ’m‚炸چںڈˆ‚ةگ¶‚ذ—§‚؟چ|‚ب‚·کV–ط‚ً‚ف‚ê‚خ‚ب‚آ‚©‚µ‚«‚©‚à پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@مق‚ن‚é‚حà’ج‚ج–ط‚جŒأ‚è‚ح‚ؤ‚µچ•–ط‚جژR‚¼–nگF‚ة‚ف‚ن پ@‚Q‚W“ْپA”شڈ¬‰®‚جکVگl‚ئ‹àگ¸“»‚ً‰z‚¦‚ؤ“’Œ³‰·گٍ‚ض‚ئŒü‚©‚¤“r’†پAپu’[‚ب‚ژ„‚حکH‚خ‚½‚ة–خ‚鉽‚â‚ç‚جگآ‚¢‘گ‚ق‚ç‚ً•¬‚«‚ ‚°‚ؤ‚ق‚‚ق‚‚ئ—N‚«ڈo‚ؤ‚î‚éگ…‚ًŒ©‚½پBکV”شگl‚ةگu‚ث‚é‚ئپA‚±‚ê‚ھگ›ڈہپAٹغڈہپA‘هگKڈہ‚جŒ¹‚ئ‚ب‚éگ…‚¾‚ئ‚¢‚سپB‚»‚ê‚ً•·‚‚ئژ„‚حژv‚ح‚¸–ô‚èڈم‚آ‚½پB‚»‚ê‚ç‚جڈہ‚جگ…Œ¹‚ئ‰]‚ض‚خپA‚ئ‚è‚à’¼‚³‚¸•ذ•iگىپA‘ه—کچھگى‚جˆê‚آ‚جگ…Œ¹‚إ‚à‚ ‚ç‚ث‚خ‚ب‚ç‚ت‚ج‚¾پBپ^‚خ‚µ‚ل‚خ‚µ‚ل‚ئژ„‚ح‚»‚ج’†‚ض“¥‚ف‚±‚ٌ‚إچs‚آ‚½پB‚»‚µ‚ؤگط‚ê‚é—l‚ة—₽‚¢‚»‚جگ…‚ً‹d‚ف•ش‚µ‹d‚ف•ش‚µٹô“x‚ئ‚ب‚ڈ¶‚ة‹d‚ٌ‚إپAژè‚ًگô‚ذپA“ھ‚ًگô‚ذپA‚â‚ھ‚ؤ• ‚ج‚س‚‚éپT‚ـ‚إ‚ةوأ‚èˆù‚ٌ‚¾پBپv‚»‚جŒمپA‹àگ¸“»‚ج’¸ڈم‚إ”شگl‚ئ•ت‚ê“’Œ³‚ض‰؛‚é‚ئ‚±‚ë‚إپu‚ف‚ب‚©‚ف‹Iچsپv‚ح•آ‚¶‚ç‚ê‚ؤ‚¢‚éپB پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<ŒQ”nŒ§‡A>‚ضپ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@<‚`‚Œ‚‚‚•‚چ‚Rپ@ ”’چھ‹›‰‘>‚ضپ@پ@ |